Home >> 地区だより >> 「これからの建設業ICT技術2025」研修会・工事論文発表会を開催
「これからの建設業ICT技術2025」研修会・工事論文発表会を開催
三島地区 企画広報委員 佐野竜司
令和7年10月3日、「これからの建設業ICT技術2025」研修会と工事論文発表会を、三島建設業協会土木災害委員会・土木施工管理技士会三島地区合同で開催しました。
開催の目的は、当協会・地区に所属している若手技術者の育成でした。「若手のレベルアップは、地元企業の継続と発展に欠かせない。」として、協会及び技士会三島地区は、今後のICT活用を踏まえた土木技術の発展に向け継続的に取り組んでいくとの考えのもと、この研修会を開催しました。
講師は技士会三島地区に所属する小野建設株式会社の常務取締役土木本部長 中村様に、昨年に引き続き担当頂きました。
研修内容は、3D-CADの魅力や実際の活用事例など、実務に即した内容を紹介し、建設業界全体のデジタル化推進に貢献する取り組みを発表して頂きました。本研修会には地区技術者45名が参加しました。
午後からは沼津土木事務所より6名、東部農林事務所より1名の方々が、研修会および工事論文発表会に参加頂きました。
工事論文発表は、加和太建設株式会社、山本建設株式会社、小野建設株式会社、土屋建設株式会社に行って頂きました。
 |
 |
加和太建設株式会社「街中における橋梁補修工事について」
河川橋梁下の狭隘な施工環境および周辺環境における仮設計画の検討、市街地における安全対策と作業効率の向上を課題とした発表でした。
対応策として仮設計画にコンパネ、シートによる養生およびクローラー式台車を使った資機材運搬により作業効率の向上を実現した。安全対策として点検口に定点カメラを設置し、リアルタイムに河川状況を確認できる体制を構築し、現場入り口開口部の侵入禁止措置として、折りたたみ式フェンスを設置し規制範囲を必要最小限に抑えて、歩行者通路を確保したという発表でした。
山本建設株式会社「残存型枠採用によるトータルコストの縮減について」
台風により被災した富士川水系血流川の護岸等の改修工事で、出水期の5月末まで2ヶ月間の工期しかなく通常施工では間に合わないため、工期短縮とコスト削減の検討を課題とした発表でした。
対応策として通常の合板型枠から残存型枠に変更する検討を行い採用した。残存型枠で施工した結果、鉄筋組立等も並行して作業出来たことや、午前中に型枠を設置して午後からコンクリートを打設するサイクルが確立でき、46%の工期短縮およびトータルコストの縮減にもつながったという発表でした。
小野建設株式会社「地質的な特性を持つ治山工事の問題点と対応策について」
平成22年に発生した台風9号により被災した駿東郡小山町北郷地内の治山工事で、現場はスコリア土質かつ急傾斜地により丁張作業や測量業務といった危険箇所に立ち入っての作業もあったため、生産性向上と安全性確保の双方を満たせるICT施工と施工性を左右するケーブルクレーンの架設位置の検討を行った内容でした。
対応策としてICT施工において現地はGNSS衛生の受信状態が悪く、杭ナビを使用してのマシンガイダンスシステムを採用した。ケーブルクレーンは適切な能力の選定と法線を理想的な位置に架設した結果、資機材の運搬速度が上がり、運搬時間を短縮することが出来たという発表でした。
土屋建設株式会社「林道の舗装工事における施工の創意工夫について」
土肥・戸田間を結ぶ土肥戸田林道(延長989m)のアスファルト舗装工事で、施工性、走行性、出来栄えを考慮した横断勾配の変更および大型車両の長距離後進による施工効率の低下や車線逸脱の危険性回避を課題とする発表でした。
対応策としてそれぞれの課題を発注者と協議した結果、勾配変更によって道路の平坦性が改善され、走行性と見栄えの良い施工が実現出来た。工事区間内の車両待避所・転回箇所不足に対し、中間地点への待避所・転回箇所を設けたことにより大型車両の後進走行の距離が当初の半分程度となり路肩からの転落、接触事故リスクが低減し作業効率が改善されたことに加え、安全性の面についても改善されたという発表でした。
 |
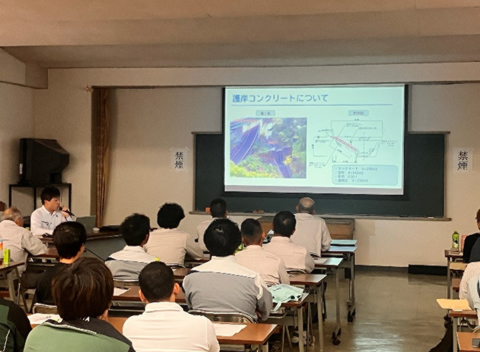 |
| 加和太建設(株) 発表者:小林 直樹 | 山本建設(株) 発表者:芹澤 剛 |
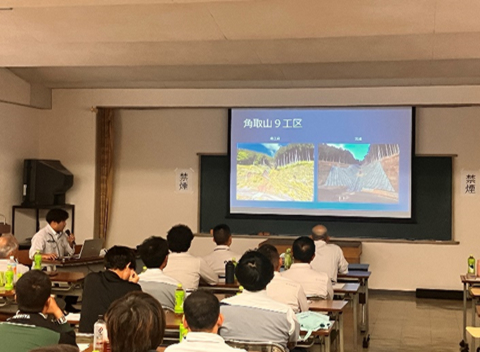 |
 |
| 小野建設(株) 発表者:大澤 駿 | 土屋建設(株) 発表者:夏賀 遼太 |